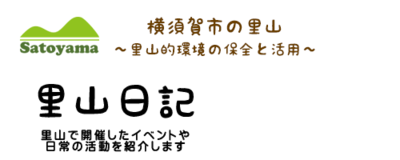平成28年度 里山林手入れ講習会(第6回)
2017年1月14日(土)9:00~
第6回 間伐した木で榾木づくり・竹を使った穂垣づくり
今年度の里山林手入れ講習会もついに最終回です 今年も草を刈り、木を切り、様々なものを手づくりしました。
今年も草を刈り、木を切り、様々なものを手づくりしました。
去年度の最終回では、大楠山山頂まで山登りをしましたが、今年度の最終回はものづくりです。何をつくるかと言うと、午前は榾木(ほだぎ)、午後は穂垣(ほがき)です。さて、これらが何だかわかりますか? 早速見ていきましょう
早速見ていきましょう
講習会最終回は天気も良く、作業には向いています。しかしこの日、大寒波が来ている真っ最中で、雪の予報が出ています 横須賀の海側に雪が降ることはあまりありませんが、確かに降ってもおかしくない寒さです
横須賀の海側に雪が降ることはあまりありませんが、確かに降ってもおかしくない寒さです
さて、榾木ですが、倒木を切ったものを使います。倒木の場所を見に行ってみましょう。
右手に沢山池を眺めながら進んでいきます。
写真が小さくてわかりづらいですが、大きな木を切り分けたものが池のほとりに置いてあります。これ、重くて運べません 今回使うものは予め切って運んであるので、とりあえず現場の中継でした
今回使うものは予め切って運んであるので、とりあえず現場の中継でした
戻ってきたところで、協力して切り分けた木を運びます。
さあ、そろそろ何だかわかってきたでしょうか?榾木とは、きのこを育てる為に使う木のことです。そう、今回はきのこの原木栽培用の木をつくり、そこに菌を入れます。今回はシイタケです 原木栽培という栽培方法は、切り株に菌を植え付けるなど色々な手法があるのですが、今回は倒木を切り出し、それを50cm~70cm程度の長さにし、そこにシイタケ菌の種を打ち込む原木栽培法です。ちなみに使う木はマテバシイです。
原木栽培という栽培方法は、切り株に菌を植え付けるなど色々な手法があるのですが、今回は倒木を切り出し、それを50cm~70cm程度の長さにし、そこにシイタケ菌の種を打ち込む原木栽培法です。ちなみに使う木はマテバシイです。
スーパーで売られているシイタケに「原木栽培」というシールが貼られているのを見たことがありますか?最近は菌床栽培といって木を使わずに栽培する事が多いようです。原木栽培のシールが貼られているものは木で栽培されたシイタケである証というわけです それでは作業の様子を見ていきましょう
それでは作業の様子を見ていきましょう
まずはドリルを使って木に穴を開けます。
 |
 |
このように穴を開けます。穴の直径は1~1.5cmといったところです。この穴にシイタケの種駒を打ち込みます 種駒とは、きのこの菌が入っている種、と考えてください。
種駒とは、きのこの菌が入っている種、と考えてください。
種駒は1.5cm程度の小さなもので、どんぐりの丸っこい側を切ったような形をしています。道に落ちていたらこれが種駒だとわかる人はおそらくいません この種駒を先ほどドリルで開けた穴にトンカチを使って打ち込みます。
この種駒を先ほどドリルで開けた穴にトンカチを使って打ち込みます。
打ち込んだものはこちらです
これを5cm幅くらいの間隔で打ち込みます。ちなみに、現代は原木栽培用の木も種駒もホームセンターなどで購入できます 自宅でも原木栽培でシイタケができる時代になりました。しかし、榾木を管理するのが結構大変なので、自宅栽培で上手くいくかは何とも言えないところです
自宅でも原木栽培でシイタケができる時代になりました。しかし、榾木を管理するのが結構大変なので、自宅栽培で上手くいくかは何とも言えないところです
さて、シイタケですが、その歴史は古く、縄文時代あたりから食べられていたと考えられています。室町時代の節用集(せつようしゅう:国語辞典のこと)に椎茸が食用であるという記述があるようですが、文献が見つけられませんでした 代わりに、栽培方法についての文献がありましたので、その一部を抜粋して紹介します
代わりに、栽培方法についての文献がありましたので、その一部を抜粋して紹介します
時は今から320年もさかのぼります。元禄10年、江戸幕府5代将軍徳川綱吉の時代です。1697年(元禄10年)に宮崎安貞が「農業全書」という農業についての本を出版しました。確か、中学校の社会で教わった気がします この本ですが、出版されたものとしては日本最古の農業書のようです
この本ですが、出版されたものとしては日本最古の農業書のようです この本は全10巻(他に巻末資料があり)で、第5巻にシイタケの記述があります。その記述がこちらです。
この本は全10巻(他に巻末資料があり)で、第5巻にシイタケの記述があります。その記述がこちらです。
「椎の木の中まではいまだくちず、皮はありて、大かたくちたるを日かげの風の吹きすかぬ所にねさせ置き、むしろこもをおほひ、上より米泔(しろみず)を頻りにかけ、しめり氣を絶やさずし置けば、椎蕈(しいたけ)多く生ずる物なり。他の朽木にも蕈(たけ)は生ゆる物なれど、木の性によりて毒なり。」
現代語では
「椎の木では内部まで枯れていなくて、樹皮がまだ残っているが、ほぼ枯れている木を日陰で風通しの悪いところに寝かせて置き、筵(むしろ)や菰(こも)で覆い、その上から頻繁に水をかけ、湿り気を絶やさないようにすれば、椎茸がたくさん生えてきます。他の木でもきのこは生えますが、原木に使う木の種類によっては毒性を持つきのこになってしまいます。」
という意味です。椎の木に生える茸だから「椎茸」と呼ばれていますが、椎の木以外にも生えます。昔は椎の木に一番多く生えていたのでしょうかね 農業全書ではこの他にも、大根(だいこん)や牛蒡(ごぼう)はこの時期にこのように植えるとよい、のような詳しい解説が書かれています。データ分析用の機器などがない時代によくここまでの研究をして記録を残したものだと脱帽です
農業全書ではこの他にも、大根(だいこん)や牛蒡(ごぼう)はこの時期にこのように植えるとよい、のような詳しい解説が書かれています。データ分析用の機器などがない時代によくここまでの研究をして記録を残したものだと脱帽です
内容からすると、現代で行っている栽培方法とそこまで違いがないように思えます。ということは、シイタケの原木栽培は320年前とほぼ変わっていないということです やはり先人の知恵は偉大ですね
やはり先人の知恵は偉大ですね
種駒を打ち込んだ榾木を運びます。これを「日かげの風の吹きすかぬ所にねさせ置き」ます。
出来ました 日当たりですが、良すぎても悪すぎてもダメで、木漏れ日が差すような場所が良いようです
日当たりですが、良すぎても悪すぎてもダメで、木漏れ日が差すような場所が良いようです 知っている方からすると、榾木は立てかけて栽培するんじゃないの
知っている方からすると、榾木は立てかけて栽培するんじゃないの と思われるかもしれませんが、栽培方法は色々とあるようで、今回は地面に置いています。立てかけるのは今年の夏の終わりから秋にかけてとのこと。これで早ければ今年の冬、遅くとも来年の春にはシイタケが生えてきます
と思われるかもしれませんが、栽培方法は色々とあるようで、今回は地面に置いています。立てかけるのは今年の夏の終わりから秋にかけてとのこと。これで早ければ今年の冬、遅くとも来年の春にはシイタケが生えてきます 農業全書では「頻(しき)りに水をかけ、湿り気を絶やさないようにする」とありましたが、種駒を打ち込まず、自然発生する菌によって栽培していたと思われるので、現代より手間暇かかっていたと考えられます。今日の榾木は水をかけたりしません。自然の雨と地面からの湿り気で十分です。
農業全書では「頻(しき)りに水をかけ、湿り気を絶やさないようにする」とありましたが、種駒を打ち込まず、自然発生する菌によって栽培していたと思われるので、現代より手間暇かかっていたと考えられます。今日の榾木は水をかけたりしません。自然の雨と地面からの湿り気で十分です。
今日の原木栽培の結果は来年です 楽しみに待ちましょう
楽しみに待ちましょう
 それでは、お昼休憩を取って午後の作業開始です
それでは、お昼休憩を取って午後の作業開始です
まずは材料を運びます。
場所は、田んぼづくり講習会で田植えをしている田んぼのすぐそばです。
さて、午後の作業を「穂垣づくり」と述べましたが、穂垣ってご存知ですか?文字通り、穂で作る垣根のことです 今回は竹で作るので、「竹穂垣」と呼ばれるものを作ります。日本庭園などに似合う、とても風流な垣根です
今回は竹で作るので、「竹穂垣」と呼ばれるものを作ります。日本庭園などに似合う、とても風流な垣根です どんなものかは出来てからのお楽しみ
どんなものかは出来てからのお楽しみ
 |
 |
まずは垣根の柱を立てる穴を掘ります。50cm~70cm程です。
 |
 |
次に、竹を真っ二つに割ります。
 |
 |
掘った穴に柱となる木を立て、土をかけます。この土をかけるという作業ですが、侮ってはいけません 通常、土は雨が降ったり人などが踏み固めたりしているので隙間が少ない、いわゆる密度が高い状態です。この掘り返した土を再び埋めても、元と同じ土の密度にはなりません。子どもの頃などに、掘った穴をその掘った土で埋めた経験がありますでしょうか?平らにならず、少し山になりませんでしたか?つまりこれは、掘って埋めたことにより、その部分の土密度が低くなったということです。密度が低いということは隙間がたくさんあるということなので、埋める時にしっかり固めないと柱が大変不安定になります
通常、土は雨が降ったり人などが踏み固めたりしているので隙間が少ない、いわゆる密度が高い状態です。この掘り返した土を再び埋めても、元と同じ土の密度にはなりません。子どもの頃などに、掘った穴をその掘った土で埋めた経験がありますでしょうか?平らにならず、少し山になりませんでしたか?つまりこれは、掘って埋めたことにより、その部分の土密度が低くなったということです。密度が低いということは隙間がたくさんあるということなので、埋める時にしっかり固めないと柱が大変不安定になります 庭に木を植えたりする時に、土を少し入れて水を流し踏み固め、また土を少し入れ水を流し踏み固め・・・を繰り返して土を盛っていきます。これは、土の密度を高めないと根が張れず十分に育たないから行う作業です。
庭に木を植えたりする時に、土を少し入れて水を流し踏み固め、また土を少し入れ水を流し踏み固め・・・を繰り返して土を盛っていきます。これは、土の密度を高めないと根が張れず十分に育たないから行う作業です。
柱を立てたら、二つに割った竹で木を挟むように置きます。
 |
 |
ドリルで竹と木に穴を開け、両側をネジで留めます。これを4段作ります。
はい、できました 一瞬でしたね
一瞬でしたね 写真マジックですね。笑
写真マジックですね。笑
写真で見ると約3秒で完成していますが、実際はここまで作るのに約2時間です。骨組みが完成したので、これから「穂垣」と呼ばれる所以となる作業をします。
「穂」とは竹の枝部分のことです。竹はところどころ枝が出ており、その部分を切った後に乾燥させておきます。材料を運んだ時の写真に何かを結んだものが写っていますが、実はこれが竹の枝を干しておいたものです 二つに割った竹を隙間ができるように固定しているので、その隙間に穂を差し込んでいきます。
二つに割った竹を隙間ができるように固定しているので、その隙間に穂を差し込んでいきます。
 |
 |
段々と形が見えてきました あとは補強と見栄えを整える作業です。まずは二つに割った竹を紐で結びます。
あとは補強と見栄えを整える作業です。まずは二つに割った竹を紐で結びます。
 |
 |
左の写真が表側、右の写真が裏側です。これは飾り結びと呼ばれる紐の結び方です 紐の結び方というのは多数あり、用途に合わせて使い分けます。「紐の結び方」で検索すると、実に様々な結び方が紹介されています。
紐の結び方というのは多数あり、用途に合わせて使い分けます。「紐の結び方」で検索すると、実に様々な結び方が紹介されています。
次に、穂の上の部分を切り揃えます。
そして・・・
完成 どうですかこの竹穂垣
どうですかこの竹穂垣 立派じゃないですか
立派じゃないですか 見栄えがよいですね
見栄えがよいですね 竹垣はその形状により呼び名があります。今回は一般的な竹穂垣ですが、日本には「金閣寺垣」や「建仁寺垣」、「光悦寺垣」、「竜安寺垣」など、固有のものもあります。「御簾垣」や「四つ目垣」などは家の垣根としても普及しており、一般的な竹垣であると思います。画像を貼りたいのはやまやまなのですが、色々と大人の事情がありますので、検索して画像を見てみてください
竹垣はその形状により呼び名があります。今回は一般的な竹穂垣ですが、日本には「金閣寺垣」や「建仁寺垣」、「光悦寺垣」、「竜安寺垣」など、固有のものもあります。「御簾垣」や「四つ目垣」などは家の垣根としても普及しており、一般的な竹垣であると思います。画像を貼りたいのはやまやまなのですが、色々と大人の事情がありますので、検索して画像を見てみてください
今回は一つしか作りませんでしたが、今後は左右に四つ目垣を配置したりと体裁を整えていきたいと思います 竹製の扉を付けて、下の川に降りられるようにするのもいいと思いません?
竹製の扉を付けて、下の川に降りられるようにするのもいいと思いません?
完成した竹穂垣の前で記念撮影
これで今年度の里山林手入れ講習会は修了です
1年にわたり講習会の様子をお伝えしてきましたが、それも今日でおしまいです このホームページを見て、何だかおもしろそうだな
このホームページを見て、何だかおもしろそうだな 、木や竹でものづくりをしてみたいな
、木や竹でものづくりをしてみたいな 、月に1度くらいは自然にふれあいたいな、と思った方はぜひ来年度の講習会にご参加ください
、月に1度くらいは自然にふれあいたいな、と思った方はぜひ来年度の講習会にご参加ください

里山はかつて人と自然が共存する環境でしたが、世の中が発達し、自然から直接恩恵を受ける生活は徐々に失われています。発達した文明を捨てる必要はないとは思いますが、失われていく里山環境を捨て置くことはできません。直接共存はしていませんので、ここは里山「的」環境としています。この里山的環境を未来へつなげていけるよう、多くの方のご参加をお待ちしております
それでは、1年間みなさまお疲れ様でした
そして、1年間お読みいただきましてありがとうございました