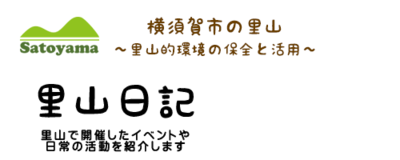令和3年度 自然観察会「野比かがみ田緑地自然観察会 "秋"」
2021年10月16日(土)10:00~12:00 野比かがみ田緑地自然観察会
野比かがみ田緑地で、秋の自然観察会を開催しました。
野比かがみ田緑地は、環境保全のため関係者以外の立ち入りをご遠慮いただいております。今回は講師と関係者立ち合いのもと、観察会を開催いたしました。
横須賀の秘境 ともいえる野比かがみ田。そのためか、定員の3倍近い応募があり、泣く泣く抽選作業をしました
ともいえる野比かがみ田。そのためか、定員の3倍近い応募があり、泣く泣く抽選作業をしました 。参加できなかった方はすいません。またの機会にご参加いただきたいと思っております
。参加できなかった方はすいません。またの機会にご参加いただきたいと思っております
 ともいえる野比かがみ田。そのためか、定員の3倍近い応募があり、泣く泣く抽選作業をしました
ともいえる野比かがみ田。そのためか、定員の3倍近い応募があり、泣く泣く抽選作業をしました 。参加できなかった方はすいません。またの機会にご参加いただきたいと思っております
。参加できなかった方はすいません。またの機会にご参加いただきたいと思っております
今回は日本トンボ学会の辻功さんと川島逸郎さんを講師としてお招きし、トンボを中心にした観察会を予定していました。
が、あいにくお天気は曇り トンボは晴れていないと飛ばないらしく、特にお目当てのアカトンボは晴れた日の午前中によく飛ぶそうです・・・
トンボは晴れていないと飛ばないらしく、特にお目当てのアカトンボは晴れた日の午前中によく飛ぶそうです・・・
 トンボは晴れていないと飛ばないらしく、特にお目当てのアカトンボは晴れた日の午前中によく飛ぶそうです・・・
トンボは晴れていないと飛ばないらしく、特にお目当てのアカトンボは晴れた日の午前中によく飛ぶそうです・・・
でもこのような悪条件の中、講師のお二人はいろいろな生きものを探してくれました(さすがです)。まず、かがみ田の入り口の水路で生き物を探しました。見つかった生き物は容器に入れて、みんなで観察しました。
| 水路で生き物の説明をする講師の辻さん | とった生き物をのぞきこむ |
 |
 |
まず入口近くの水路で、シマアメンボをとってくれました。このアメンボは川の上流域に住んでおり、一見黒一色のようですが、カメラやスマフォで撮影して拡大して見ると、なんと、古代エジプト様の模様が (この画面ではお見せできず残念です)。この模様のため「シマ」アメンボと名がついているそうです。
(この画面ではお見せできず残念です)。この模様のため「シマ」アメンボと名がついているそうです。
下の画像が水路で見られた生き物たちです。
| シマアメンボ | コオイムシ |
 |
 |
| ホタルの幼虫 | ヨシノボリ |
 |
 |
水路の生き物を楽しんだ後、いよいよかがみ田の中に入っていきます。なお、足元がぬかるんでいるので長靴は必須アイテムです。
かがみ田の中では参加者は二つのグループに分かれて、ルートを変えて観察しました。ある程度整備されている道も、道なき道も、ずんずん進みます。
 |
 |
講師の方は写真などを見せながら、わかりやすく丁寧に説明してくれました。
 |
 |
ジョロウグモの巣があちこちにありました。巣にいる目立つ大きな個体はメスで、同じ巣に小さいオスがひっそりと居候しています。オスはうかつにメスに近づくとガブリと食べられてしまうので、メスの脱皮直後や食事中にスキをみてしのびより交尾をするそうです。そんな話を聞いた後、参加者の方たちは巣を見るとオスを探し、「あ、ここにいる」と声をあげている人もいました。このホームページを御覧の皆さんも、ジョロウグモの巣を見つけたら、ぜひオスを探してみてください。

さらに散策していくと、キリギリスやコカマキリを見つけました。参加者のお子さんがおそるおそる触っています。
| キリギリス | コカマキリ |
 |
 |
そして、とうとうトンボ発見!アオモンイトトンボが田んぼの上を飛んでいました。講師の方がサッと素早く網で捕まえました(さすがです)。わかりにくいですが、お腹の先端(お尻の方?)が水色なので「アオモン」イトトンボと呼ぶそうです。細くて、胸とお腹の鮮やかな水色が目立ち、きれいなトンボです。
その後、木の葉に停まっていたアオイトトンボを参加者の方たちが見つけました(細くて目立たないのに・・・スゴイ!)。講師の方がまたも網で捕まえました。講師の方は「目が多いと(大勢いると)見つけやすい」と言っていました。一人で散策もいいですが、何人かで見ることで発見もある、と観察会の意義を感じました。
トンボに触れる人たちは、トンボをつかみながら観察しました。参加者のお子さんが観察したトンボを、他のお子さんにそっと手渡ししています こんな風にやさしく触れながらトンボを近くで観察できました。
こんな風にやさしく触れながらトンボを近くで観察できました。
 こんな風にやさしく触れながらトンボを近くで観察できました。
こんな風にやさしく触れながらトンボを近くで観察できました。
最後に出発地のかがみ田入口まで戻ってきました。ここで水路の中におおきなカワニナを発見。カワニナは淡水にいる細長い巻貝で、ゲンジボタルのエサになります。幼虫もいて、餌もあるので、来年の6月ごろにまたホタルが飛んでくれるでしょう

最後に講師の方々から、観察会で見られた生き物の説明がありました。トンボはあまり見られませんでしたが、ホワイトボードやトンボの標本を使って説明をしてくれました。
 |
 |
こうして約2時間の観察会はあっという間に終了しました。次回は春に